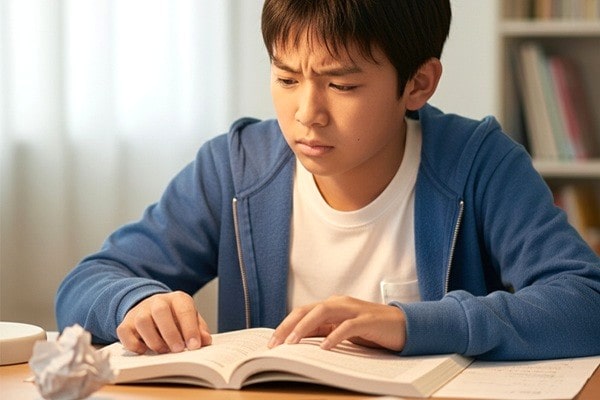
「うちの子、教科書を読むのにすごく時間がかかる…」
「漢字や英単語を、何度練習しても覚えられない」
「簡単な計算ミスがどうしてもなくならない」
中学生になり、学習内容がぐっと難しくなったことで、お子さんの「勉強の困難さ」が以前より目立ってきたと感じることがありますよね。
もしかしたら、その困難さは「本人の努力不足」や「怠慢」が原因ではないかもしれません。
学習障害(LD)は、知的な発達に遅れがないにもかかわらず、特定の学習スキル(読む、書く、計算するなど)の習得がとても難しい状態を指します。
本人は一生懸命やっているのに、脳の特性上、特定の部分でつまずきやすいのです。
大切なのは、その困難さを「根性で乗り越えさせる」ことではなく、お子さんの特性に合った「やり方」や「工夫」を見つけることですね!
この記事では、宮入個別指導塾がこれまで見てきた生徒さんたちの例も踏まえながら、学習障害(LD)の主な特性に合わせた具体的な勉強方法と、ご家庭でできるサポートのコツを解説します。
①まず確認!学習障害(LD)とは?
②「読む」のが苦手な生徒(読字障害)の勉強法
③「書く」のが苦手な生徒(書字表出障害)の勉強法
④「計算する」のが苦手な生徒(算数障害)の勉強法
⑤ご家庭でできるサポートと保護者の心構え
⑥学校や専門家、塾との連携
①まず確認!学習障害(LD)とは?
文部科学省の定義にもある通り、基本的には「全般的な知的発達に遅れはない」ことが前提です。
それにもかかわらず、「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」といった能力のうち、特定のものの習得や使用に著しい困難を示す状態を指します。
中学生で困難が目立つ理由
小学校時代は、比較的シンプルな暗記や、保護者の方の手厚いサポート、本人の頑張りでなんとかカバーできていたかもしれません。
しかし、中学生になると状況は一変します。
こんなふうに、学習の「量」と「質」が変化することで、それまで隠れていた困難さが一気に表面化してくるのです。
種類の解説
文字を読むのが極端に苦手。教科書を読むのに時間がかかる、読み間違える、どこを読んでいたか分からなくなる(行を飛ばす)、読めても内容が頭に入ってこない、など。
■書字表出障害(ディスグラフィア):
文字を書くのが極端に苦手。鏡文字になる、漢字や英単語の形を覚えられない、マス目や罫線にうまく収めて書けない、板書を写すのが異常に遅い、など。
■算数障害(ディスカリキュリア):
計算や数の概念理解が極端に苦手。簡単な筆算や暗算ができない、繰り上がり・繰り下がりで混乱する、時計や九九がなかなか覚えられない、数学の文章題の意味が理解できない、など。
俳優のトム・クルーズさんが読字障害(ディスレクシア)で、台本を読み込むのに苦労したという話は有名ですね!
他にも著名人、歴史上の偉大な人物でこういった学習障害を抱えていた例も意外とあります。
ですから「学習障害があるから立派な大人になれない」なんてことはないですし、
これから解説しますが、工夫次第でハンデを乗り越えることは可能です。
希望をもっていきましょう!
②「読む」のが苦手な生徒(読字障害)の勉強法
文字を読むことに困難があるお子さんは、教科書や問題文を読むだけで疲弊してしまい、肝心の内容を理解する前にエネルギー切れを起こしてしまいます。
文字を「音」に変換する処理(音韻処理)がスムーズにいかない、文字の形を正確に認識するのが難しい、といった脳の働きが関係していると言われます。
工夫1:「耳」からインプットする
読むのが苦手なら、他の感覚を使いましょう。
今は便利なツールがたくさんありますから、使わない手はありません!
■音声読み上げ機能:
教科書や参考書をスキャンし、PCやタブレット、スマホの読み上げソフト(アプリ)を使って聞かせる。
■オーディオブック:
文学作品などは、オーディオブックを活用するのも手です。
■英語学習:
特に英語は「音」が重要です。
まずはリスニングやシャドーイング(音声を聞きながら真似して発音する)から入り、「音と文字が一致する感覚」を掴むことを優先します。
工夫2:「目」の負担を減らす
視覚的なストレスを減らす工夫も有効です。
■拡大コピー:
教科書や問題集を拡大コピーし、行間を広くとる。
■リーディングトラッカー:
読む行以外を定規や厚紙で隠し、今読んでいる行に集中できるようにする。
③「書く」のが苦手な生徒(書字表出障害)の勉強法
「書く」のが苦手なお子さんは、特に定期テスト前の「英単語や漢字の暗記」で苦労します。
「10回ずつ書いて覚えなさい!」という昔ながらの根性論は、残念ながら逆効果になることが多いです。
文字の形を正確に思い出す(想起する)のが難しい、あるいは、頭では分かっていても手先を思い通りに動かすのが難しい(不器用さ)などが考えられます。
「書く」作業のハードルを下げる
書くこと自体が目的でない場合は、思い切って「書かない」選択肢も検討します。
■PC・タブレットの活用:
漢字や英単語の練習はタイピングで行う。
考えをまとめる(作文やレポート)のも、まずはPCで打たせる。
■板書は写真で:
学校の許可が必要ですが、板書を写すのに必死で先生の話が聞けないなら、タブレットで撮影させてもらう。
あるいは、板書できている友だちのノートをコピーさせてもらう。
文房具やノートを工夫する
マス目が大きいノートや、罫線が太くハッキリしたノートを選ぶ。
鉛筆はBや2Bなど、濃く滑らかに書けるもの(力を入れすぎなくて済む)を使う。
暗記の方法を変える
■漢字学習:
「へん」や「つくり」などパーツに分解し、パズルのように組み合わせる。
「さんずい」は水に関係ある、など意味とセットで覚える。
■英単語学習:
単語カード(表に英語、裏に日本語)を作り、視覚で覚える。
何度も声に出して「音」で覚える。
④「計算する」のが苦手な生徒(算数障害)の勉強法
「数学」は中学生にとって大きな壁です。
特に計算が苦手だと、方程式や関数など、その後の単元すべてでつまずいてしまいます。
原因として、「数の概念」そのもの(数や量のイメージ)が掴みにくい、あるいは、計算の手順(例:筆算のくり上がり)を一時的に覚えておく「ワーキングメモリ」の働きが弱い、といった可能性が考えられます。
具体物や「図」で可視化する
■数直線や模型:
正負の数や方程式の「移項」で混乱したら、数直線を積極的に利用したり、天秤など実際のオブジェクトを使ってイメージさせる。
■図やグラフ:
文章題は、必ず登場する物や関係性などを図に書き起こす練習をする。
「速さ・時間・距離」なども図で整理させます。
手順を「見える化」する
ワーキングメモリの負担を減らします。
■計算手順のカード化:
筆算の手順や、方程式を解く手順をカードに書き出し、それを見ながら解く練習をする。
■電卓の使用:
学校との相談が必要ですが、「計算そのもの」ではなく「文章題の立式」が目的の場合、計算は電卓に任せるという配慮も考えられます。
徹底的にスモールステップで進む
例えば「連立方程式」なら、「①式を整理する」「②片方の文字を消去する」「③代入する」…という手順のうち、今日は「①だけを完璧にする」など、一つのステップに絞って練習します。
③ご家庭でできるサポートと保護者の心構え
ここまで具体的なテクニックをお伝えしてきましたが、それ以上に大切なのが、ご家庭での「土台」となる関わり方です。
「なぜできないの?」ではなく「どこで困ってる?」と声をかける
以前、私が接したことのあるK君(中1)の話です。
彼は「書く」ことに強い苦手さがあり、定期テスト前の英単語練習に苦戦していました。
ある日、お母さんが「勉強、終わったの?」とノートを見ると、練習したはずの英単語がスペルミスだらけ。
お母さんは思わず「こんなに間違えて!ちゃんと覚える気あるの!?」と叱ってしまったそうです。
しかし、私がそのノートをよく見ると、間違ってはいるものの、ページいっぱいにビッシリと練習した「格闘の跡」がありました。
「書くこと」自体に人一倍エネルギーが必要なK君が、逃げずにこれだけ取り組んだ。
その事実が何より重要です。
私はお母さんにこう伝えました。
「間違いを指摘する前に、まず『うわ、こんなにビッシリ書いたんだ。しんどかっただろ、お疲れさん』と、そのプロセスを認めてあげてください」と。
保護者の方からすれば、間違いだらけのノートは不安になるかもしれません。
でも、お子さん本人は「努力してもできない」こと、そして「努力を認めてもらえない」こと、その二重の苦しさを抱えています。
「なぜできないの?」という結果への問い詰めではなく、「どこで困ってる?」「どこがやりにくかった?」と、プロセスに寄り添う声かけに変えてみてください。
「できた!」という小さな成功体験を積み重ねる
学習障害のお子さんは、学校生活の中で「自分はできない」という劣等感を抱きやすい環境にいます。
自己肯定感が下がると、勉強への意欲そのものが失われてしまいます。
ご家庭では、「正解する経験」を意図的に作ってあげることが大切です。
例えば、英単語なら「今日はこの3つだけ完璧に覚える」と決め、その3つができたら思い切り褒める。
数学なら、教科書の例題レベルの簡単な問題を解き、「できた!」という感覚を味わわせる。
その小さな成功体験の積み重ねが、「自分もやればできるかもしれない」という次への意欲につながります。
集中できる学習環境を整える
特性上、注意が散漫になりやすいお子さんもいます。
視界に入るポスターや漫画などを減らす。
タイマーを使い「15分集中→5分休憩」のように、短時間集中を繰り返す。
こうした環境整備も、有効なサポートの一つですね!
⑥学校や専門家、塾との連携
ここまで読んで、「家でやるのは、なんだか大変そう…」と感じたかもしれません。
その通り、すべてをご家庭だけで抱え込む必要はまったくありません!
学校との連携
まずは学校の担任の先生、あるいは特別支援教育の先生に相談することが第一歩です。
お子さんの困難さを共有し、授業やテストでどのような「合理的配慮」が可能か(例:テスト時間の延長、別室受験、電卓持ち込み、読み上げ機能の許可など)を相談してみましょう。
塾との連携
宮入個別指導塾では、生徒さん一人ひとりに合わせた完全1対1指導を行っています!
生徒さんの特性を理解した上で、「これならできる」というスモールステップを設定し、学習方法を一緒に試行錯誤していきます。
ご家庭だけで不安でしたら、ぜひお気軽にご連絡下さい♪


●英語の長文読解や複雑な文法が登場する
●板書量が増え、授業スピードも上がる